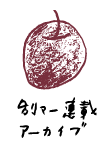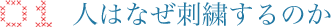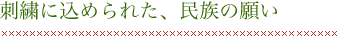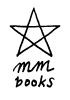Special Issue 別マー特集
更新日 2008/11/28
murmur magazine vol.3「刺繍特集」連動企画 刺繍は魔法
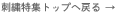

世界の人々の生活に息づく「刺繍」。
ヨーロッパ、アジア、ロシアに、日本――。
地域によって趣きは違えども、
どれも思わず見入ってしまうものばかりです。
それにしても人はなぜ、刺繍をしてきたのでしょうか?
そのルーツを探るべく、刺繍や染織の歴史に詳しい
文化女子大学名誉教授・道明三保子さんに
お話をうかがいました。
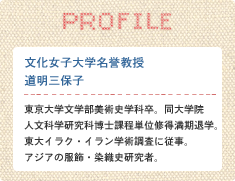
――そもそも人々は、なぜ刺繍をするようになったのでしょうか?
道明さん(以下敬称略) 刺繍にはたくさんの実用的なメリットがありました。まずは衣服の補強。糸の方向がさまざまな刺繍は、引っ張りに対して非常に強く布を補強します。
民族衣装では、衣服の擦り切れやすい部分を補強するために、襟や袖、裾に民族ごとの吉祥文様などを刺繍してきました。
――なるほど。
道明 そこに刺繍することで、民族や地域を識別する役割も果たしていたとも言われます。また、それらと同時に大切にされてきたのが、民族のアイデンティティを顕示したり、魔除けにするなど、思いを刺繍に託すという行為です。
――そういえば、日本の特攻服やスカジャンにも刺繍がありますね。ああいうものも、魔除けだったり、自分たちの存在を表現する伝統の流れだったりするのでしょうか。
道明 そうですね。とくにアジアの庶民的な刺繍では、村に代々伝わる民族文様をもとに、身近に存在した動物などを交えながら、自分の願望や夢などを絵で描くような気持ちで縫い表されてきたのです。
中国の明・清の時代には、皇帝の礼服「龍袍(りゅうほう)」に必ず強いものの象徴である、5つの爪をもつ龍の刺繍が施されました。確かに、龍や虎は特攻服や学ランなどでも好かれるモチーフ。絶対的な強さへの憧れや自己顕示の表現としては、関連性があるかもしれません。
自分の思いを具現化する刺繍。それを身に着けることが自分の表現や主張につながっていく――。「今日こそ気合いを入れたい!」なんていうときには、刺繍の服や小物でキメてみる!?


Photograph by Yasuo Ichige
Interview & Text by murmur magazine